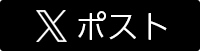民法では、被相続人との関係によってどの相続人がどれだけの遺産を相続できるのかが定められています。これが「法定相続分」です。
 |
被相続人の配偶者は常に相続人になります(内縁関係の場合は相続人になりません)。
第1順位:被相続人の子、その次に被相続人の父母・祖父母(直系尊属)、被相続人の兄弟姉妹という順で相続人になります。
第2順位:被相続人の子が被相続人の死亡以前に亡くなっている場合には、被相続人の孫が相続します。これを「代襲相続」といいます。
第3順位:兄弟姉妹が以前に死亡していた場合も同様に、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が相続します。
| 優先順 | ケース | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 第1位 | 被相続人の配偶者と被相続人の子がいる場合 | ・配偶者に2分の1 ・子に2分の1 (複数いる場合は、全体の2分の1を頭割り) ・ただし、摘出でない子は摘出子の2分の1 ・直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれない |
| 第2位 | 被相続人の配偶者と被相続人の父母・祖父母がいる場合 (子・孫・ひ孫といった直系卑属がいない場合) |
・配偶者に3分の2 ・父母・祖父母に3分の1 (複数いる場合は、全体の3分の1を頭割り) ・兄弟姉妹は相続人になれない |
| 第3位 | 被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹がいる場合 (子・孫・ひ孫といった直系卑属も父母・祖父母もいない場合) |
・配偶者に4分の3 ・兄弟姉妹に4分の1 (複数いる場合は、全体の4分の1を頭割り) ・ただし、片親違いの兄弟姉妹は被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1 |
例外的なケース
法定相続人がいない場合
法定相続人がいない場合、たいした遺産がなければ、そのまま放置されるケースも多いかと思います。
もし、被相続人にお金を貸していた人がいたり、「相続人ではないが、親族だし、生前の被相続人の面倒を見てきたから」といった理由で 財産をもらいたい人がいれば、家庭裁判所に「相続財産管理人」という人を選んでもらい、返済を受けたり、「特別縁故者」として 遺産の一部または全部をもらうことができるかもしれません。
もし、こういった人が誰もいない場合には、遺産は国のものになります。
法定相続人でも相続できない場合
被相続人を殺害したり、被相続人を強迫して遺言を書かせたり、被相続人の遺言を偽造したりした場合は、 相続権を失います(相続欠格)。
また、被相続人がある人物に遺産を相続させたくないときには、生前に家庭裁判所に請求し、遺言でその意思を示すことで推定相続人の相続権を没収できます。
(廃除) 廃除に関してですが単に「相続させたくない」という意思があるだけではできず、被相続人を虐待したといった事情が必要です。
また、「生前に家庭裁判所に請求する」または「遺言で廃除の意思表示をする」、その上で家庭裁判所が認めてはじめて「廃除」となります。
相続したくない場合
被相続人が多額の借金を残している、生前から関係が悪かったといった理由から、「相続はしたくない」というケースもあるかと思います。
そういった場合、家庭裁判所で一定の手続をとることで、相続人ではなくなることができます(相続放棄)。
相続放棄の手続は、簡単に言うと、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に行う必要がありますが、「相続人としての優先順位が高い人が相続放棄をしたので、そこではじめて自分が相続人になった」といった場合はそのことを知ってから、「何も遺産はないと思って放置していたら、実は莫大な借金があることを知った」といった場合は借金があると知ってから、それぞれ3か月以内で構いません。 ただし、遺産を既に受け取っていたような場合には、相続放棄はできません。